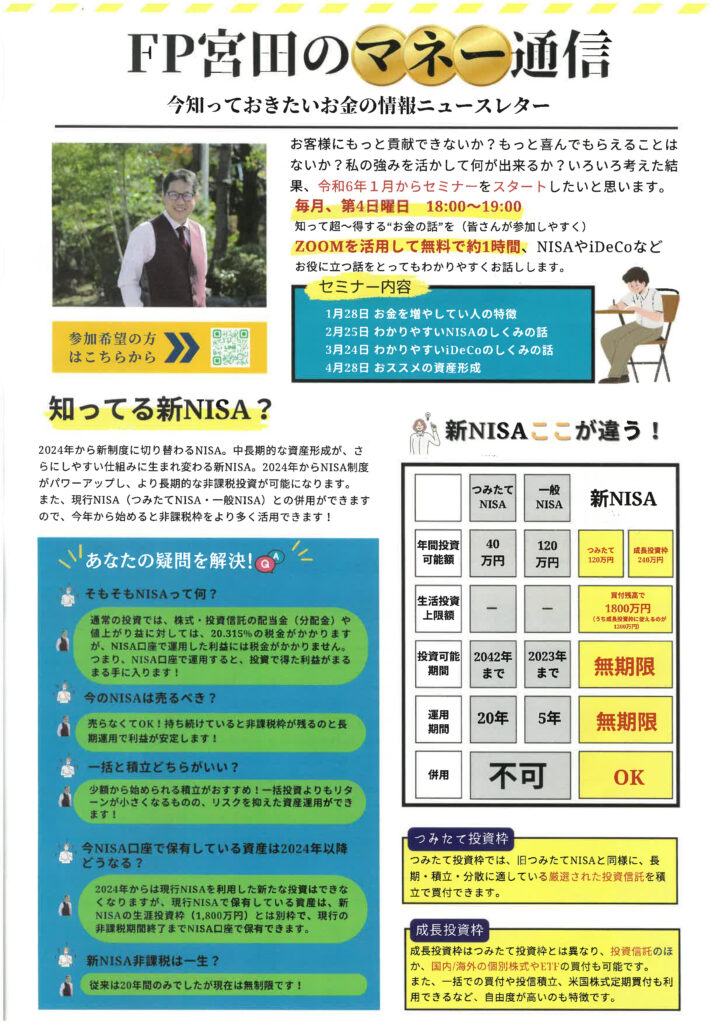先週、富山県に行ってきました。
岡山県でも有名な税理士事務所の先生(A)とコラボで講演をさせていただきました。
その方と話をしてびっくり。
A:娘が水戸に住んでるんです。千波町と言うところに。旦那さんが全国転勤の仕事なんで。
私:旦那さんはどちらにお勤めなんですか?
A:〇という会社なんです
私:えーっ!私の娘の旦那も同じ会社ですよ
講演が終わって…
A:岡山にも宮田さんと同じような財務の仕事をしている人がいます。今増えてるんですかね?
私:財務の勉強と仕事してる人、岡山で1人います。Bさんという熱心な方です
A:えーっ!私が知っているのも、Bさんですよ。財務に詳しいのでコラボしようと思ってるんですよ。
初めてお会いしたAさんと、2人も共通の知り合いがいるなんて…
こういうのを、引き寄せの法則っていうんですかね~
1月に…「日本の三名園」に
兼六園・後楽園・偕楽園に行ってきました。
中国の唐の時代に白居易(白楽天)という著名な詩人がいました。
白居易の詩の中に、自然の美しい景色を示す「雪月花」という言葉があります。
この雪月花に基づいて、雪の兼六園、月の後楽園、花の偕楽園という、当時のキャッチフレーズのようなものが作られました。
雪の兼六園、月の後楽園、花の偕楽園というキャッチフレーズから、パンフレットに兼六園、後楽園、偕楽園が日本三名園として紹介されるようになったと…
兼六園
兼六園の原型は、すでに江戸時代初期にはあったと伝えられています。
それが整備され兼六園と名付けられたのは、前田家13代藩主前田斉泰の時代。
兼六園は1年中観光客で賑わいます。
何といっても有名なのは雪吊り。
兼六園の冬は降雪に見舞われます。
その兼六園の樹木がいつまでも美しさを保っているのはこの雪吊りがあるから。
冬の兼六園の雪と雪吊りのコントラストは、日本ならではの美しさを感じさせてくれます。
後楽園
後楽園は、岡山藩主池田綱政により造営されました。
後楽園が完成したのは1700年。
後楽園と名付けられたのは明治時代になってからのことですが、偕楽園や兼六園よりも200年以上早く作られたことがわかります。
後楽園では中秋の名月を楽しむ「名月鑑賞会」が毎年開催されています。
偕楽園
偕楽園は、水戸徳川家9代藩主徳川斉昭により作られました。
徳川斉昭は「烈公」と称されるとおり幕末の過激思想を持つ大名の一人で、徳川斉昭は幕末史を彩る重要人物の一人に数えられています。
偕楽園といって、まず思い浮かぶのは梅。
花の偕楽園と言われるとおり、偕楽園には3000本の梅が植えられ、2月下旬から3月にかけて毎年盛大に梅まつりが開催されています。